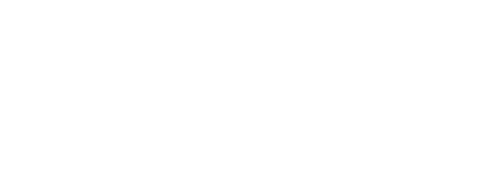風邪をひいたときに「ビタミンCをとれば回復が早まる」と聞いたことはありませんか?
ニンジンを食べれば暗闇でも目がよく見える、そんな話も子どもの頃に一度は耳にしたかもしれません。さらに「日光を浴びて骨を強くしよう」とすすめられるのは、ビタミンDのおかげです。
普段何気なく口にする食べ物の中には、こうした「体に必要不可欠な小さな成分=ビタミン」がたくさん含まれています。けれど、その名前の背景や、ビタミンという考え方がどう誕生したのかを深く考える機会は、意外と少ないのではないでしょうか。
A、B、Cというシンプルなアルファベットの裏側には、実は「何が足りないのか」を探し続けた科学者たちの物語と、食事と健康の関係を巡る壮大な発見の歴史が隠されています。

栄養不足が病気の正体だった
今でこそ、ビタミン不足が体調不良の原因になることは当たり前の知識ですが、科学的に解明されたのはわずか100年ほど前のことです。
20世紀初頭、壊血病やくる病といった病気が、単なる体の不調ではなく、特定の栄養素が不足することで発症することが明らかになりました。
1912年、ポーランドの化学者カジミール・フンクは、米ぬかから健康維持に不可欠な成分を発見し、これに「ビタミン(vitamine)」と名付けました。この発見が、現代の栄養学の大きな礎となったのです。
偉大なる発見の連鎖
栄養と健康の関係が少しずつ解き明かされるなか、タンパク質が注目されたのは1838年ごろでした。しかしその後、白米中心の食生活を送っていた日本の船乗りたちが、謎の病に倒れるケースが多発します。この原因究明に挑んだのが、日本の医師・高木兼寛とオランダの医師・クリスティアン・エイクマンでした。
彼らは「たんぱく質の不足ではなく、白米だけの食生活が問題だ」と突き止め、後にこれがビタミンB1不足による脚気であることがわかります。
フンクの「ビタミン発見」は、この流れの中で大きな意味を持ちました。ビタミンは、たった少量でも体にとって欠かせない栄養素であり、不足すれば命に関わることを示したのです。
そして1929年には、デンマークの生化学者ヘンリック・ダムが「血液を正常に凝固させる役割」を持つビタミンKを発見。この功績により彼は1943年、ノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

ビタミンたちの驚くべき役割
それでは、私たちが日常的に耳にするビタミンの役割を、改めて整理してみましょう。
- ビタミンA:夜間視力や免疫力を支えるだけでなく、皮膚や細胞の新陳代謝にも欠かせません。ニンジンやカボチャ、レバーなどに多く含まれています。
- ビタミンB群:ひとつではなく、B1・B2・B6・B12など多くの種類があります。エネルギー代謝や脳の働き、肌の健康まで幅広くサポートします。穀物、野菜、卵、肉類に多く含まれています。
- ビタミンC:柑橘類に多く含まれ、壊血病を防ぐだけでなく、免疫力の維持や鉄分の吸収、肌の健康にも欠かせません。ストレスや体調不良のときには特に積極的にとりたいビタミンです。
- ビタミンD:日光を浴びることで皮膚で合成され、骨の健康や免疫機能をサポートします。脂の多い魚やきのこ、強化食品にも含まれています。
- ビタミンE:強力な抗酸化作用で細胞の老化を防ぎます。ナッツ類や種子、植物油などから摂取できます。
- ビタミンK:血液の凝固を助け、骨の健康にも関わります。緑黄色野菜、とくにほうれん草やケールに豊富です。

食事は、科学の結晶です
ビタミンという小さな成分が、どれほど大きな影響を体に与えているか、改めて実感できたのではないでしょうか。
普段のサラダ、焼き魚、果物。何気ない一食の中に、健康を守るための“生命の鍵”がしっかり詰まっています。ビタミンは単なる栄養素ではなく、科学者たちが命をかけて解き明かしてきた「健康の土台」です。
A、B、C、D、E、K――シンプルな文字の並びが、私たちの健康と日々の暮らしを、今も静かに支えています。